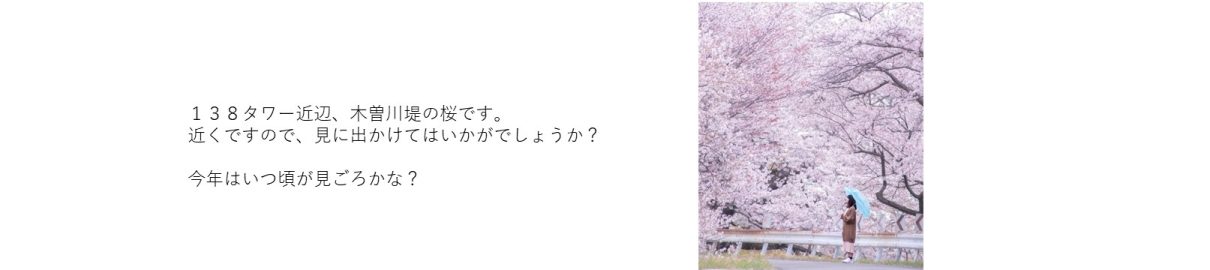最近、大河ドラマ「べらぼう」では喜多川歌麿、10月公開映画「おーい、応為」では葛飾北斎親子。江戸時代の絵師が登場し、私たちは絵師の生き様を知ることができます。
もう一人、江戸時代中期に京都で活躍した、伊藤若冲という絵師がいました。この若冲は、「動植綵絵」が有名です。庭で数十羽の鶏を飼い、すぐには写生をせず、鶏の生態をひたすら観察し続けました。朝から晩まで徹底的に見つめ、一年が経ち見尽くしたと思った時、ついに「神気」を捉え、おのずと絵筆が動き出したといいます。鶏の写生は2年以上も続き、その結果、若冲は鶏だけでなく、草木や岩にまで「神気」が見え、あらゆる生き物を自在に描けるようになったそうです。
また、生き物の視点から見える情景も描きました。例えば、池の畔にいるカエルが見る池の魚や上方の樹に止まっている小さな虫など、とてもリアルに、生命が息づく情景を描きました。無名の小さな虫、見向きもされない雑草など、「生きとし生けるもの」すべてを受け入れました。『自分に関係ないものを排除するのではなく、この世のものすべてを受け入れる』、つまり”共生”をモットーとしたのです。排他的な考えは好ましくありません。ましてや自己中心的あるいは自分のテリトリーだけを大事にすることは愚かなことではないでしょうか。この”共生”という観点が、総合的な人間力向上へと導いていくものと思います。


南天雄鶏図(動植綵絵、宮内庁三の丸尚蔵館蔵)