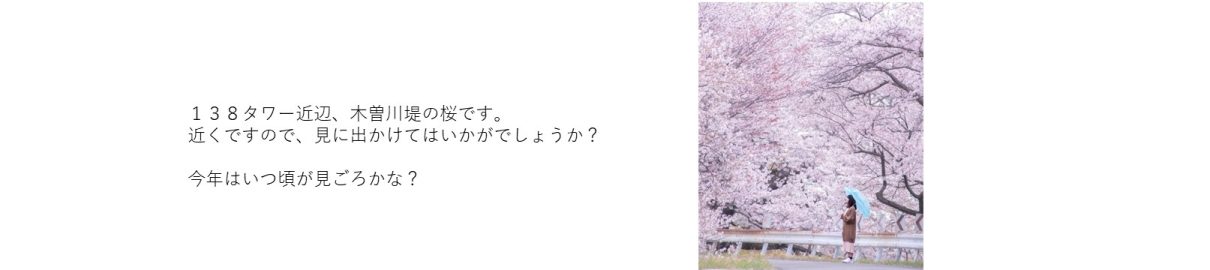町会長協議会 連区長 佐塚 篤

皆さん こんにちは。「住んで良かった里小牧」の区長の佐塚です。
木曽川町連区の連区長の任期は2年で、もう一年 連区長です。よろしくお願いします。
里小牧の紹介です。
里小牧の「牧」は、牧場・・などに使われているように、草原の地に付けられている名前。
木曽川が運んだ砂で、自然につくられた砂地で、その上に葦や雑草が生え、生い茂っていた小さな草原地帯でした。土地の開発が進むと人口も増加し、草原地に次第に家を建て、住民が増えていきました。そんな頃、誰いうとなく、小牧の里と呼ぶようになっていきました。
里小牧には電車道という通りがあります。賀茂神社から木曽川西小学校を北進、北方町方面へ通っている道を電車道と呼んでいます。現在は、名鉄尾西線の玉ノ井駅で終わっていますが、昔は北方宝江まで通っていました。木曽川町内にはじめて私鉄道が敷設されたのは1914年、尾西鉄道が新一宮から奥町、玉ノ井、木曽川橋(宝江)の区間 8.7キロを開通したのが始まりです。1925年 尾西鉄道は名鉄と合併して名鉄尾西線になりました。はじめは、蒸気機関車でしたが、1924年電化になり、柳橋(名鉄名古屋始発駅)から木曽川橋に直通の急行を運転した時期もありました。更に 宝江は対岸の笠松港と同様、物資の荷揚げ場所でもあり、県内各地に運び出す必要から、尾西線を木曽川橋から堤防外の川渕まで延長して「木曽川港駅」をつくりました。川を下ってきた舟からは、石、砂利、砂などが陸揚げされて貨物車に積み替えられて各地へ工事用資材として運ばれていました。常滑方面からは、常滑焼などを満載した大船が接岸して荷揚げされている様子も見られたそうです。この付近には 陶器、植木鉢、庭石を売る店もできました。木曽川西小学校の南門にある大石もこの電車で運ばれてきた思い出の石です。